一般に、ラミネート設計には 2 つの主なルールがあります。
1. 各ルーティング レイヤーには隣接する参照レイヤー (電源または形成) が必要です。
2. 隣接する主電源層とグランドは、大きな結合容量を確保するために最小限の距離に保つ必要があります。
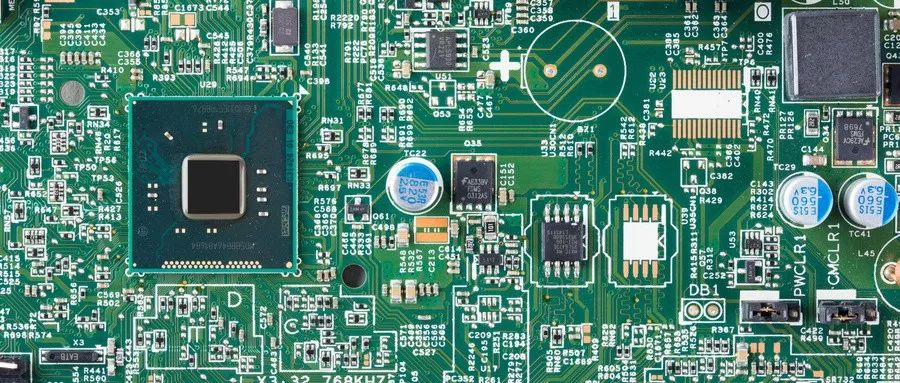
以下は 2 層から 8 層のスタックの例です。
A.片面PCB基板と両面PCB基板積層
2層構造の場合、層数が少ないため積層の問題はありません。EMI放射対策は、主に配線とレイアウトから考慮されます。
単層および二層プレートの電磁両立性はますます重要になっています。この現象の主な原因は、信号ループの面積が大きすぎることです。これにより、強い電磁放射が発生するだけでなく、回路が外部干渉に対して敏感になります。ラインの電磁両立性を向上させる最も簡単な方法は、重要な信号のループ面積を縮小することです。
重要信号:電磁両立性の観点から、重要信号とは主に強い放射を発生し、外界に対して敏感な信号を指します。強い放射を発生する信号は通常、クロックやアドレスなどの低レベル信号のような周期信号です。干渉に敏感な信号とは、低レベルのアナログ信号を指します。
単層および二重層のプレートは通常、10KHz 未満の低周波シミュレーション設計で使用されます。
1) 同じ層で電源ケーブルを放射状に配線し、線路長の合計を最小にします。
2) 電源線とアース線を互いに近づける場合、アース線を主要な信号線のできるだけ近くに配線します。これにより、ループ面積が小さくなり、差動モード放射の外部干渉に対する感度が低下します。信号線の隣にアース線を追加すると、面積が最小の回路が形成され、信号電流は他のアース経路ではなく、この回路を経由することになります。
3) 二層基板の場合は、基板の反対側に、下の信号線に近接させ、信号線に沿ってできるだけ太いアース線を敷設します。これにより得られる回路面積は、基板の厚さと信号線の長さの積に等しくなります。
B.4層の積層
1. Sig-gnd (PWR)-PWR (GND)-SIG;
2. GND-SIG(PWR)-SIG(PWR)-GND;
これらの積層設計の両方において、潜在的な問題は、従来の1.6mm(62mil)というプレート厚にあります。層間隔が広くなるため、インピーダンス制御、層間結合、シールド効果が向上するだけでなく、特に電源層間の間隔が広くなるとプレート容量が減少し、ノイズフィルタリングの効果が低下します。
最初の方式は、通常、基板上のチップ数が多い場合に用いられます。この方式はSI性能は向上しますが、EMI性能はそれほど良くなく、主に配線などの細部によって左右されます。主な注意点:最も密度の高い信号層に層を配置することで、放射の吸収と抑制を促進します。また、20Hルールを反映するためにプレート面積を増やします。
2つ目の方式は、通常、基板上のチップ密度が十分に低く、チップ周囲に必要な電源銅箔を配置するのに十分な面積がある場合に使用されます。この方式では、PCBの外層はすべて層状構造で、中間の2層は信号層と電源層です。信号層の電源は幅の広い配線で配線されるため、電源電流のパスインピーダンスが低く、信号マイクロストリップパスのインピーダンスも低く、外層を介した内部信号放射も遮蔽できます。EMI制御の観点から、これは利用可能な4層PCB構造の中で最良のものです。
主な注意点:信号層と電源層の中間層は間隔を広くし、配線方向は垂直にすることでクロストークを回避します。適切な制御盤エリアを確保し、20Hルールを遵守します。配線のインピーダンスを制御する場合は、電源とグランドの銅線アイランドの下に配線を慎重に敷設します。さらに、電源または配線中の銅線は、DCおよび低周波の接続性を確保するために、可能な限り相互接続する必要があります。
C.6層の板の積層
高密度チップと高クロック周波数の設計には、6層基板の設計を検討する必要があります。推奨される積層方法は以下のとおりです。
1.SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG;
この方式では、信号層とグランド層を隣接させ、電源層とグランド層を対にすることで、積層構造により良好な信号整合性を実現しています。これにより、各配線層のインピーダンスを適切に制御でき、両層とも磁力線を良好に吸収します。さらに、完全な電源供給とフォーメーションの条件下で、各信号層に優れたリターンパスを提供します。
2. GND-SIG-GND-PWR-SIG-GND;
この方式は、デバイス密度がそれほど高くない場合にのみ適用されます。この層は上位層の利点をすべて備えており、最上層と最下層のグランドプレーンは比較的完全であるため、より優れたシールド層として利用できます。電源層は、主要コンポーネントプレーンではない層の近くに配置する必要があります。そうすることで、最下層のグランドプレーンがより完全になるためです。そのため、EMI性能は最初の方式よりも優れています。
まとめ:6層基板の方式では、良好な電源・グランド結合を得るために、電源層とグランド層の間隔を最小限に抑える必要があります。しかし、62ミルの基板厚と層間間隔の縮小を実現したとしても、主電源層とグランド層の間隔を非常に小さく制御することは依然として困難です。第1の方式と第2の方式と比較して、第2の方式はコストが大幅に増加します。そのため、通常は第1のオプションを選択します。設計時には、20Hルールとミラー層ルールに従ってください。
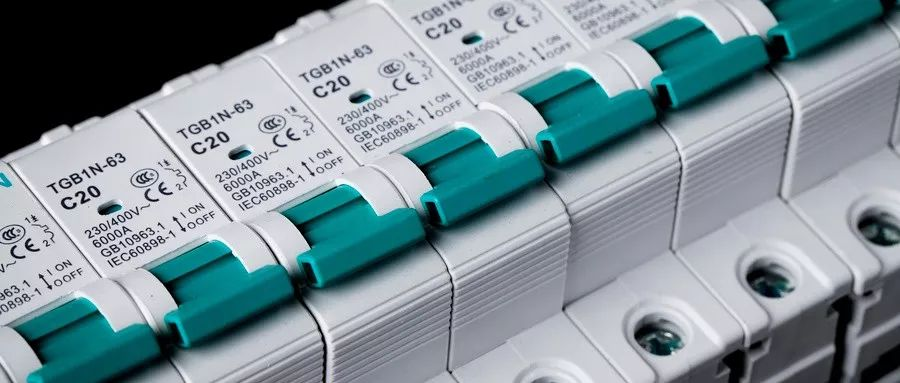
D.8層の積層
1. 電磁吸収能力が低く、電力インピーダンスが大きいため、この積層方法は適していません。その構造は次のとおりです。
1.信号1部品面、マイクロストリップ配線層
2.信号2内部マイクロストリップ配線層、良好な配線層(X方向)
3.地面
4.信号3ストリップライン配線層、良好な配線層(Y方向)
5.信号4ケーブル配線層
6.パワー
7.信号5内部マイクロストリップ配線層
8.信号6マイクロストリップ配線層
2. これは第3の積層モードのバリエーションであり、基準層を追加することでEMI性能が向上し、各信号層の特性インピーダンスを適切に制御できます。
1.信号1部品面、マイクロストリップ配線層、良好な配線層
2.地層、優れた電磁波吸収能力
3.信号2 ケーブル配線層。良好なケーブル配線層
4.電源層、およびそれに続く地層は優れた電磁波吸収を構成します5.接地層
6.信号3 ケーブル配線層。良好なケーブル配線層
7.大きな電力インピーダンスによる電力形成
8.信号4マイクロストリップケーブル層。良好なケーブル層
3、多層接地基準面の使用により地磁気吸収能力が非常に優れているため、最適なスタッキングモードです。
1.信号1部品面、マイクロストリップ配線層、良好な配線層
2.地層、優れた電磁波吸収能力
3.信号2 ケーブル配線層。良好なケーブル配線層
4.電源層、およびそれに続く地層は優れた電磁波吸収を構成します5.接地層
6.信号3 ケーブル配線層。良好なケーブル配線層
7.地層、優れた電磁波吸収能力
8.信号4マイクロストリップケーブル層。良好なケーブル層
使用する層数と層の使用方法は、基板上の信号ネットワークの数、デバイス密度、PIN密度、信号周波数、基板サイズなど、多くの要因によって異なります。これらの要因を考慮する必要があります。信号ネットワークの数が多いほど、デバイス密度が高くなり、PIN密度も高くなるため、可能な限り高い信号周波数設計を採用する必要があります。良好なEMI性能を得るには、各信号層に独自のリファレンス層を設けることが最善です。
投稿日時: 2023年6月26日







